相続相談室 ≫ 二世帯住宅
二世帯住宅 特例
■概要
相続税は相続した遺産全てにかかるわけではありません。遺産総額から相続人毎の「基礎控除額」を差し引いた部分が課税対象となります。
つまり遺産総額よりも「基礎控除額」が上回れば相続税は発生しないのです。
しかし、今回の大改正(H27年1月1日相続分以降)により「基礎控除額」が縮減されます。
よって、遺産総額が「基礎控除額」を上回るケースが多くなります。
つまり、これまで相続税とは無縁だと思っていた世帯にも相続税が課税される可能性がある、
という事です。
ただ、準備さえしておけば節税は可能です。その代表例が『小規模宅地等の特例制度』です。
これは相続した不動産に相続人が引き続き居住する場合、被相続人と相続人が生計を共にする場合等には税金的に優遇措置を施そうという国の配慮からくる相続税の減税制度です。
この制度を上手に利用すれば大幅な節税に繋がるのです。
この制度を活用するにあたり、今回の改正によって制度変更がありましたので解説いたします。
■小規模宅地等の特例について
相続発生時の相続財産の価値を下げることで相続税の課税を回避または減額するための手法です。
母親はすでに他界、高齢の父親と同居するか別居するかが大きな分かれ道になります。
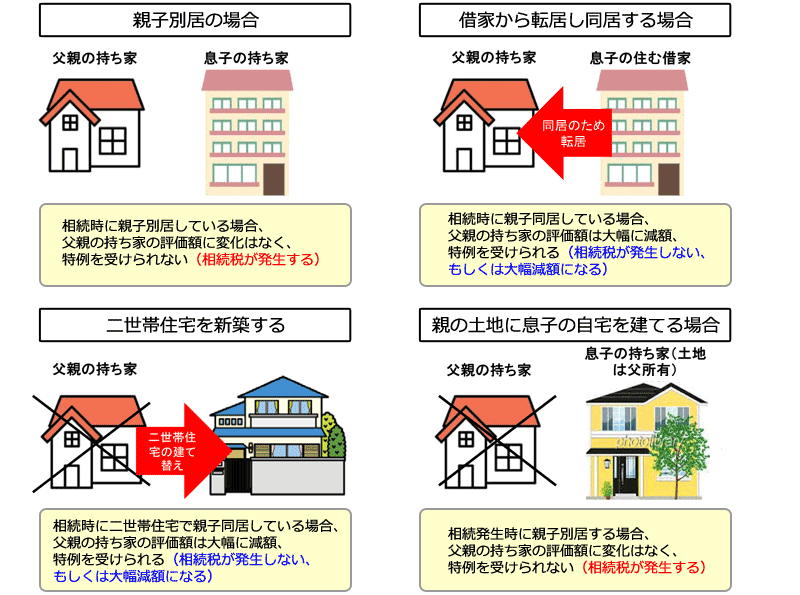
■住宅の構造に関する取扱いの変更
これまでは二世帯住宅の構造によって特例を受けられるケースと受けられないケースがありました。内部で行き来が出来ない構造になってる場合、同居とは認められず特例が使えませんでした。
しかし、平成26年1月からは構造上区分されている住宅でも特例が使えるようになり、更に平成27年1月からは特例が使える居住地の面積が240㎡から330㎡に拡充されます。
【改正前】
改正前は構造上完全に区分された部分に親が居住していた場合、その部分に対応する宅地のみが特例の適用の対象とされていました。
したがって、2階建ての区部住宅で1階部分に親が、2階部分に長男が居住していた場合、長男は被相続人と1階で同居していたとは認められないため、この敷地を相続した場合には、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けられませんでした。
【改正後】
改正後は親の居住用として利用されていた区分二世帯住宅でも長男が親と同居していたものとみなして、その長男の居住部分も特例の範囲に追加されることとなります。
したがって、内階段で行き来できない構造の二世帯住宅で、長男がこの宅地等を取得した場合についても、1階、2階に対応する敷地全体が小規模宅地等の評価減の特例の適用対象となります。